伝統工芸職人になるにはどうすればいい?その種類や方法を紹介
織物や染め物、陶磁器や漆器、刃物など、日本各地には数々の伝統工芸があります。
その製法技術や美しさには、海外からも称賛され、需要があったりするものです。
テレビなどでよく紹介されるのが、そんな伝統工芸品の製作に携わる職人さんたちの姿。
ひたむきに技術を身につけ、研鑽しつづける姿を見て、「自分も伝統工芸品を作る職人になりたい」と思う人もいるのではないでしょうか。
この記事では、まず日本の伝統工芸にはどのようなものがあるかを紹介。職人になるための方法などについても見ていきましょう。
そもそも「伝統工芸品」とはどんな物のこと?
日本には、全国各地でさまざまな伝統工芸品が作られています。
一般的に伝統工芸品とは、ある土地で決まった材料を使い、代々受け継がれている技術や製法などによって作られている日用品などのことをいいます。
手作業ならではのぬくもりや繊細さ、使い勝手の良さなどに惹かれる人も多く、最近ではさまざまな伝統工芸品が海外でも人気を集めています。
法律上は、次のいずれにも当てはまるものを「伝統工芸品」と呼びます。
- 生活に豊かさと潤いをもたらす工芸品である
- 機械で大量生産されるものでなく、職人の手作業で持ち味が生まれている
- 原料や技術・技法が、原則100年以上受け継がれている
- 作られているのが一定の地域で、ある程度の規模がある
2019年には3つの工芸品が新たな「伝統的工芸品」として認められました。
伝統工芸品一覧|日本各地で受け継がれる伝統的な手工芸品
伝統工芸品には、さまざまな種類があります。
| 種類 | 主な伝統工芸品(抜粋) |
|---|---|
| 陶磁器 | 益子焼(栃木)、九谷焼(石川)など |
| 漆器 | 津軽塗(青森)、鎌倉彫(神奈川)など |
| 金工品 | 南部鉄器(岩手)、高岡銅器(富山)など |
| 木工品 | 大館曲げわっぱ(秋田)、仙台箪笥(宮城)など |
| 竹工品 | 高山茶筌(奈良)、勝山竹細工(岡山)など |
| 織物 | 結城紬(茨城、栃木)、西陣織(京都)など |
| 染め物 | 加賀友禅(石川)、京友禅(京都)など |
| その他の繊維製品 | 伊賀くみひも(三重)、京繍(京都)など |
| 和紙 | 美濃和紙(岐阜)、越前和紙(福井)など |
| 人形 | 宮城伝統こけし(宮城)、博多人形(福岡)など |
| 文具・用具 | 伊勢形紙(三重)、熊野筆(広島)など |
| 仏壇 | 山形仏壇(山形)、飯山仏壇(長野)など |
| その他工芸品 | 江戸切子(東京)、播州毛鉤(兵庫)など |
政府に指定されているのは現状255品目ですが、条件を満たしていないなどの理由で認定されていない伝統工芸品はたくさんあります。
伝統工芸品の職人になるにはどうすれば?まずは情報収集から
転職してその世界に入ることは可能なんでしょうか?
携わりたい伝統工芸が決まっているのなら、その伝統工芸品に関する団体や店舗などに問い合わせをしてみるのが一番の近道。
しかし、まだ特に「これ」と決まっていない場合は、次のようなサイトで伝統工芸に携わる求人情報を手に入れることができます。
| サイト名 | 特徴 |
|---|---|
| 四季の美 | 地域や種別から絞り込み検索可能 |
| 日本仕事百貨 | 各仕事についての取材記事と求人情報を掲載 |
| COLE | 工芸品に関する情報サイト。求人情報も |
一般的な職種と同じようにハローワークや各種転職サイトで募集されているケースもありますし、地域に密着した情報サイトなどでの公募、店舗や工房などで直接募集を行っているケースもあります。
また、伝統工芸の一部には、後継者育成事業の費用をクラウドファンディングで募るものも。
翌1月には、岐阜県内外から2名が新たな職人見習いとしてスタートすると発表されました。
クラウドファンディングは直接の募集情報ではありませんが、後継者のニーズがあるかどうかの判断材料にすることができます。
「伝統工芸のどれか」ではなく、自分が興味を持って続けていける、深く魅力を感じる伝統工芸品を探して、直接問い合わせをすることをおすすめします。
各地で伝統工芸品づくりの体験や職人による実演などのイベントが行われているので、参加したり話を聞いたりするのも1つの方法です。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 東京手仕事(TOKYO Teshigoto) | 実演販売やワークショップなどの情報あり |
| 三条鍛冶道場(新潟) | 和釘づくりや包丁研ぎなどの鍛冶技術が体験できる |
| 高岡地域地場産業センター | 鋳物または漆器の体験教室あり |
| 飛騨高山まちの体験交流館 | 一位一刀彫のワークショップなどを開催 |
| 備前焼陶友会 | 土ひねり体験ができる窯元などの紹介 |
| 高岡地域地場産業センター | 鋳物または漆器の体験教室あり |
| 砥部焼観光センター炎(えん)の里 | 絵付け体験のほか、職人の技を見学するコーナーあり |
ここで紹介しているのはほんの一例。ぜひいろいろと調べて探してみてください。
技術を学べる学校やスクールも、公立のもの、民間のものなど各地にあります。
| 名称 | 特徴など |
|---|---|
| 会津漆器技術後継者訓練校 | 蒔絵、塗の各専攻研修生を隔年で募集 |
| 紬織物技術支援センター(栃木) | 結城紬の機織りの後継者を育成 |
| 江戸切子スクールHANASHYO’S | 江戸切子職人が経営するスクール。職人養成コースあり |
| 石川県立輪島漆芸技術研修所 | 未経験者は基礎技術の修得を2年間かけて行う。 |
| 京都市産業技術研究所 伝統産業技術後継者育成研修 |
陶磁器や漆、西陣織、京友禅など多彩なコースあり |
| 沖縄工芸振興センター | 「織物」「紅型」「漆芸」「木工芸」の4つのコースあり |
ただし後継者育成については、国の補助金を使って行われているものもあります。上記の内容も継続して行われるとは限らないので、行われているかどうかは必ず確認してください。
ものづくりの技術を学びたい、という場合、失業している人を対象にしたハローワークの職業訓練では、地域によっては木工や竹工芸、陶磁器の製造などを学べたりします。
伝統工芸品の職人には誰でもなれるわけじゃない
伝統工芸品の中には、「一子相伝」や「一家相伝」として、技法は子孫のみで受け継ぐのが伝統となっているものもあります。
その場合、他人が技法を授かることはできません。
| 一子相伝 | 能代春慶(秋田)、相良人形(山形)、結桶(東京)、一国斎高盛絵(広島)、倉敷はりこ(岡山)、讃岐提灯(香川)、小鹿田焼(鹿児島)など |
|---|---|
| 一家相伝 | 堤人形(宮城)、甲州印伝(山梨)など |
一子相伝の場合、文字通り後継者は子孫のうち1人だけ。一家相伝の場合は、その家の人間のみで代々守り継がれているのです。
ただ、たった1人で伝統を受け継いできた場合、後継者が途絶えるとその伝統工芸品の製作も途絶えてしまいます。それを惜しんで、復興活動などを行う地域も。
たとえば秋田県の能代春慶は、平成22年に製造が途絶えてしまいましたが、4年後には後継者掘り起こしなどについての勉強会が開かれています。
また、逆に需要が伸びたために一子相伝をやめたという伝統工芸もあります。
奈良県の高山茶筌は、もともと一子相伝だったものを、生産が追いつかないことなどを理由に地域の産物として作るようになりました。今では300人ほどの職人が茶筅づくりに携わっています。
しかしこれは、職人になるためのものではなく、その人の熟練した技術を認めるためのもの。
産地で12年以上の経験がないと、試験を受けることができません。
伝統工芸の職人になるなら、伝統工芸の現状も把握しておこう
日本各地の伝統工芸品の価値は、これまでずっと大切に守られてきたわけではありません。
戦後、生活の西洋化や大量生産・大量消費、使い捨て文化の広がり、農林業の衰退、労働に対する考え方の変化、生活様式の変化など、こうしたさまざまな理由によって伝統工芸品のニーズは減少し、産業は衰退の一途をたどってきたのです。
実に5分の1近くにまで減少しています。
国は昭和48年に、伝統的工芸品産業を振興させる目的で法律を制定し、技術や技法の維持と発展に向けて経費補助や認定表示などの制度を作りました。
そして近年、日本の伝統工芸品の技術の高さや利便性、デザインなどが海外で評価されたり、環境に配慮したLOHAS(ロハス)などの考え方が流行したりといった背景から、一部では伝統工芸品の良さを見直す風潮も見られるようになってきました。
職人さんって儲かるんですか?
それに、需要の減少で生活が成り立たないからとやめてしまったり、後継者不足になったりするケースもあるのです。
伝統工芸品は、単価は安くないとは言え、一度に大量に売れるものでもありません。
そもそも私たちが伝統工芸品を「高い」と感じてしまうのは、大量生産・使い捨ての社会に慣れすぎてしまっているからだと言えます。
伝統工芸品はどれも厳選した材料、しかも限られた材料を使って、手間と時間を掛けて作られているもの。価格を特に高く設定しているわけではないのです。
お金を目当てに伝統工芸品の世界を目指しているなら、考え直した方がいいかもしれません。
しかし、まったく別の土地・業界から来た人が、その土地で新たな文化を創り出すこともあります。
たとえばその伝統工芸品の良さを新たに世界に発信するためのアイデアを持っていたり、伝統を守りつつ斬新な切り口で製品や使い方などを提案できたりする人。
もしかしたら、衰退しかけている伝統工芸品の救世主として活躍できるかもしれません。
まずはその伝統工芸品や育まれてきた土地、歴史などを知って、好きになること。そこから始めましょう。
伝統工芸品の職人になるなら情報収集から始めよう
社会の動きに合わせてニーズが失われたり、材料が確保できないなどの理由で廃れてしまうものもありますが、優れた技術や製品を後世に残すべきだ、と思う人も多いですよね。
それをぜひとも自分も手伝いたい、という人も。
全国には、国が認定したものだけでも250以上の伝統工芸が息づいています。伝統工芸職人になりたいなら、まずは情報を集めることが不可欠です。
その工芸品がどのようにして生まれたか、どのような技法、工程で作られているか、後継者を外から受け入れるニーズがあるのかどうかなど、まずは「知る」ことからはじめましょう。
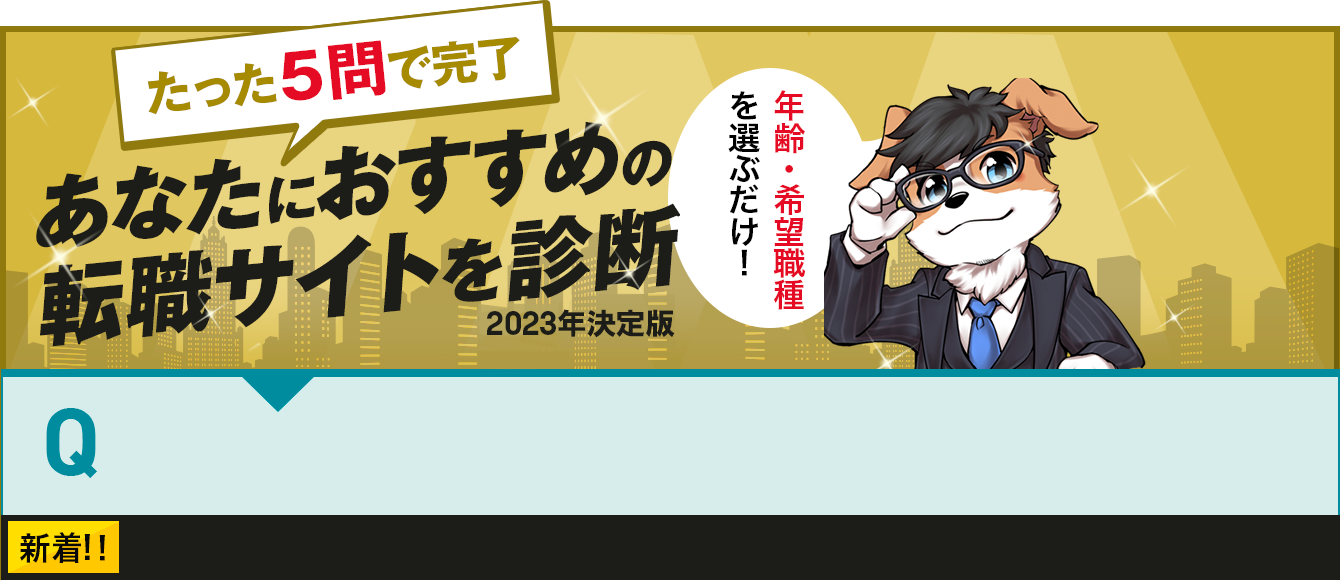

- DODA 第二新卒歓迎!働きながら業界トップレベルの技術を学ぶモノづくりエンジニア募集
- リクナビNEXT 約8割が未経験からのスタート!大手商社でグローバルに活躍できる人材を募集中!
- マイナビ転職 女性の働きやすさ抜群!有給消化率98%の有名メーカーで事務スタッフを募集中
- エン転職 フレックス制で自由な社風!未経験者OK!平日夜・土日面接OK
- @type 残業月20h未満/年休125日/定着率95%【入社祝金アリ】







絵や彫刻などの美術品とは違いますか?